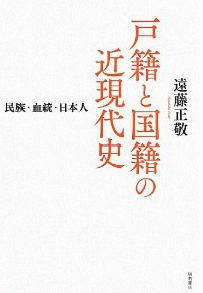著者の略歴-1972年生。早稲田大学大学院政治学研究科博士課程修了。博士(政治学)。早稲田大学台湾研究所招稗研究員、宇都宮大学、埼玉県立大学等で非常勤講師。専攻は政治学、日本政治史、東アジア国際関係史。著書に『近代日本の植民地統治における国籍と戸籍-満洲・朝鮮・台湾』明石書店、2010年。主要論文に「対時する二つの新秩序『大東亜新秩序』と『大西洋憲章』における植民地主義のゆくえ」松村史紀・徐顕分・森川裕二編著『東アジアにおける二つの戦後』国際書院、2012年、「満洲国における朝鮮人の就籍問題-治外法権撤廃と無籍朝鮮人対策」『アジア経済』第52巻第10号、2011年10月、等。 戸籍制度は一種の身分を示すものであり、憲法14条に反すると言われながら、我が国では戸籍を後生大事にしている。 マスコミだって、芸能人の結婚と言えば、入籍したことを高らかに知らせる。 おそらく戸籍とは我が国に固有の制度だと、多くの人は知らないのだろう。 戦前からの置き土産だった戸籍を、韓国と台湾が廃止してしまったので、いまでは世界中で我が国だけが戸籍制度を死守している。
戸籍とは<市町村の区域内に本籍を定める1つの夫婦およびこれと氏を同じくする子>を単位として編纂される公文書である。 戸籍には戸籍筆頭者からはじまって、同じ氏つまり同じ姓を名乗る者が記載される。 戸籍は住所や同居人の記述は不要であり、家族の身分を記すものだ。 身分証明書としては不完全であり、住民票としても使えない。 もっぱら国家が国民を支配するために作られたものである。 戸籍には続柄が記載されている。続柄とは、戸籍筆頭者から見た関係を示すものだ。 ここで嫡出子と非嫡出子が区別される。 また、外国人は戸籍にのらないので、外国人との間に生まれた子供は微妙な立場におかれる。 しかも、父系にするか母系にするか、または両系にするかで、問題が異なってくる。 二重国籍を避ける意味だろうが、父親が外国人だと生まれてくる子供は、長いあいだ日本国籍に入らなかった。 氏を同じくする男女と言うが、我が国の歴史上では男女同氏はそれほど古いものではない。 夫婦が氏を同じくすることは日本古来の伝統であるかのような理解が少なくない。だが、「夫婦同氏」なる原則は、明治国家において始まったものである。明治期に庶民一般が氏の使用を義務化されてから、ただちに夫婦も同一の氏を称すべきものとされたわけではない。 1876年3月17日、太政官指令は「婦女夫に嫁するも仍ほ所生の氏を用ゆべきこと。但其夫の家を相続したる上は夫家の氏を称すべき事」として、妻は夫の家に入ってからも旧姓を維持すべきものとされていた。(中略)明治民法に基づく家制度確立の前夜のことであるが、戸主の統率する家に嫁いできた婦女に戸主と同じ氏を名乗らせなかったのは、戸内に元々同居していた家族との区別を氏によって示す意図があったと考えられる。すなわち、家系を示すという氏の役割が優先されたため、夫婦といえども別氏とすることを容認せざるを得なかったのである。P53 明治の民法が成立して初めて、男女同氏が法文化されたのである。 それまでは韓国などと同様に、男女別氏が原則だった。 我が国では、現在の戸籍を古くからあるものだと考えがちであるが、戸籍は戦前の天皇制国家体制が成立する過程で、擬制の血縁に基づいた家族国家をつくるために創出されたのである。 明治国家にとって、まず税収の基礎として、そして、徴兵の名簿として戸籍が考えられた。 住所地で日本人を区別すると、居住している人は全員を日本人とせざるを得なくなる。 居住地とは異なる本籍という架空の所在地を生み出したのは、ひとえに本籍地という虚構に日本国籍を関連づけるためだった。 言い替えると、日本国民を区別するために戸籍が整備されたのである。 戸籍は決して身分登録証明書ではない。
それでも、概して次のような共通点があり、それが日本の戸籍制度と著しい対照をなしている。第一に、身分登録が個人を単位として行われる点である。今日、日本においてみられる戸籍制度改革(解体といってもよい)の主張は、日本も家族単位から個人単位の制度へと改めるべきだというものが大半である。第二に、個人の身分の変動について、事件ごとに登録される点である。個人の出生、婚姻、離婚、死亡などを統一的に記録するのではなく、出生登録簿、婚姻登録簿というように事件別に記録簿を編製する形式である。米国では州による差異はあるものの、基本的に出生証書、婚姻証書、死亡証書など、事件ごとに個人を単位とした証書を作成し、これらの証書を基にして出生登録簿、婚姻登録簿を編製する方式がとられている。第三に、身分登録の対象となる事項が必要最小限だという点である。欧米では出生、婚姻、死亡以外は、せいぜい離婚、養子縁組、認知などに及ぶ程度であり、戸籍のような個人の親族関係の登録はない。P65 本サイトは核家族から単家族へと転じるべきだと論じてきた。 本サイトの言う核家族とは、氏を同じくする男女とその子供たちという家族であり、まさに戸籍が言う家族の単位こそ核家族である。 子供は一対の男女からしか生まれない。 その意味では核家族が自然のように見える。 しかし、核家族を戸籍という形で制度化することは、氏に個人を纏めてしまうことであり、個人の平等に反する。 だから現代の先進国では、核家族単位の登録制度ではなく、個人単位の登録制度を取っているのである。 男女が誰と共に住もうと、法律は同居者が誰であるかに立ち入るべきではない。 国家は人口統計を取る必要があるだろうが、それは氏を同じくする男女を単位とするべきではない。 あくまで個人を単位とすべきである。 我が国では、戸籍の他に、住民票があり、住基ネットがあり、運転免許証があり、そのうえに国民総背番号をおも導入しようとしている。 身分証明書であれば、運転免許証で充分である。 沖縄の戸籍再製事業には、沖縄のあらゆる法制度が米国の掌中で作動するという国際環境にあって、戸籍事務を通じてなしくずし的に沖縄と本土との一体化を図り、本土復帰への道筋を見出そうという日本政府の意図があった。
これを見るにつけ、日本政府は沖縄住民の法的地位についてみせたような慎重性と柔軟性をなぜ朝鮮人・台湾人の国籍処理において発揮することがなかったのかという疑問を禁じえない。沖縄と旧植民地における国籍政策に差別化をもたらした日本国家の基準は、やはり戸籍に公示される「日本人」としての「血統」にあったのか。だが、そうした理解は戦後の沖縄戸籍の復元過程にみられた国籍や本籍をめぐるカオス的状況を考えれば無理がある。やはり、沖縄の本土復帰と沖縄住民の「日本人」への再統合という主権国家の要請を、戸籍を最大限に利用して実現へとつなげるための機会主義的政策であったといわねばならない。つまり、それだけ戸籍が融通盤に政治権力によって駆使される「国民」選別の装置であるということである。P274 戸籍の意味・役割は、筆者の言うとおりである。 それにしても、戸籍は考察の彼方に置かれている。 家制度や国籍の研究は多いのに、戸籍の研究は少ない。 佐藤文明の「戸籍がつくる差別」があるくらいだ。 政治学専攻の筆者は、この少ない分野を埋めるべく、本書を上梓したという。 1972年生まれの筆者は、今年で42歳になる。 職業はと見ると、早稲田大学台湾研究所非常勤次席研究員(本書上梓時は招聘研究員)、宇都宮大学非常勤講師、埼玉大学等で非常勤講師だとある。 戸籍という研究主題を選んでしまったから、メインストリームを歩けないのだろうか。 何だか悲しい気分になってくる。 (2014.5.12)
参考: J・S・ミル「女性の解放」岩波文庫、1957 下田治美「ぼくんち熱血母主家庭 痛快子育て記」講談社文庫、1993 ジョン・デューイ「学校と社会・子どもとカリキュラム」講談社学術文庫、1998 大河原宏二「家族のように暮らしたい」太田出版、2002 G・エスピン=アンデルセン「福祉国家の可能性」桜井書店、2001 G・エスピン=アンデルセン「ポスト工業経済の社会的基礎」桜井書店、2000 J・F・グブリアム、J・A・ホルスタイン「家族とは何か」新曜社、1997 磯野誠一、磯野富士子「家族制度:淳風美俗を中心として」岩波新書、1958 エドワード・ショーター「近代家族の形成」昭和堂、1987 黒沢隆「個室群住居」住まいの図書館出版局、1997 S・クーンツ「家族に何が起きているか」筑摩書房、2003 奥地圭子「学校は必要か:子供の育つ場を求めて」日本放送協会、1992 信田さよ子「脱常識の家族づくり」中公新書、2001 高倉正樹「赤ちゃんの値段」講談社、2006 デスモンド・モリス「赤ん坊はなぜかわいい?」河出書房新社、1995 ジュディス・リッチ・ハリス「子育ての大誤解」早川書房、2000 フィリップ・アリエス「子供の誕生」みすず書房、1980 伊藤雅子「子どもからの自立 おとなの女が学ぶということ」未来社、1975 エリオット・レイトン「親を殺した子供たち」草思社、1997 ウルズラ・ヌーバー「<傷つきやすい子ども>という神話」岩波書店、1997 編・吉廣紀代子「女が子どもを産みたがらない理由」晩成書房、1991 塩倉裕「引きこもる若者たち」朝日文庫、2002 ピーター・リーライト「子どもを喰う世界」晶文社、1995 ニール・ポストマン「子どもはもういない」新樹社、2001、 杉山幸丸「子殺しの行動学:霊長類社会の維持機構をさぐる」北斗出版、1980 矢野智司「子どもという思想」玉川大学出版部、1995 瀬川清子「若者と娘をめぐる民俗」未来社、1972年 赤川学「子どもが減って何が悪い」ちくま新書、2004 浜田寿美男「子どものリアリティ 学校のバーチャリティ」岩波書店、2005 本田和子「子どもが忌避される時代」新曜社、2008 鮎川潤「少年犯罪」平凡社新書、2001 小田晋「少年と犯罪」青土社、2002 リチヤード・B・ガートナー「少年への性的虐待」作品社、2005 広岡知彦と「憩いの家」「静かなたたかい」朝日新聞社、1997 高山文彦「地獄の季節」新潮文庫、2001 マイケル・ルイス「ネクスト」㈱アスペクト、2002 服部雄一「ひきこもりと家族トラウマ」NHK出版、2005 塩倉 裕「引きこもる若者たち」朝日文庫、2002 瀬川清子「若者と娘をめぐる民俗」未来社、1972 ロイス・R・メリーナ「子どもを迎える人の本」どうぶつ社、2005 瀬川清子「若者と娘をめぐる民俗」未来社、1972年 イヴォンヌ・クニビレール、カトリーヌ・フーケ「母親の社会史」筑摩書房、1994 下田治美「ぼくんち熱血母主家庭 痛快子育て記」講談社文庫、1993 芹沢俊介「母という暴力」春秋社、2001 編・吉廣紀代子「女が子どもを産みたがらない理由」晩成書房、1991 信田さよ子「父親再生」NTT出版、2010 岡田尊司「母という病」ポプラ新書、2012 岡田尊司「父という病」ポプラ社、2014 遠藤正敬「戸籍と国籍の近現代史」明石書店、2013 佐藤文明「戸籍がつくる差別」現代書館、1984
|
|||||||||||||||