著者の略歴−1947年、愛知県に生まれる。1972年、京都大学文学部国史学科卒業。1981年、京都大学大学院博士課程国史学専攻単位取得満期退学。現在、京都女子大学文学部教授、京都大学博士(文学) 主要著書・論文:『思想史における近世』(思文閣出版、1991年)、『江戸武士の日常生活』(講談社、2000年)、「近世のパスポート体制」(『史窓』第62号、2004年)、「”七つ前は神のうち”は本当か」(『国立歴史民俗博物館研究報告』第141集、2008年)、「近世の思想と文化」(『日本の歴史 近世・近現代編』ミネルヴア書房、2010年) 子供の扱われ方は、時代によって変化してきた。
「7歳までは神のうち」と言われるが、これは近代になって普及した俗説であるという。 そして、中世までは子供は無頓着に扱われたが、江戸時代の中頃から大切に扱われるようになったと、本書は言う。 変化した理由も実に説得的に展開されている。 7歳までは神のうちは俗説だが、7歳が幼児と大人との境界年齢だとするのは、すでに養老律令に見ることができる。 中国でも7歳を境界年齢としていたので、我が国でもそれに習ったのだろう。つまり7歳未満はまだ善悪の反断ができないので、責任無能力者と扱ったのだろう。 これは現代でもよく分かる感覚である。今でも幼稚園児に常識的な判断を期待することはない。 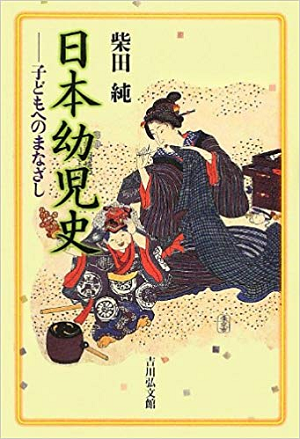
7歳未満を責任無能力としてきたし、現実的にも聞きわけのない年齢だから、7歳までは神のうちという俗説が広まったのだろうと思う。
しかし、面白いことに養老律令には、90歳以上も責任無能力者と扱っているのだ。今日の暴力老人のことを考えると、昔の人も何か分かっていたのだろうか。
子供の話に戻ると、石山寺縁起絵巻などでは子供は裸で描かれている。これは7歳までの子供は、 身分がない者として扱われていたので衣類を描けなかったのだという。 中世に限らず前近代では、身分制がはっきりしており、 身分によって着る衣装もはっきり区別されていた。7歳までの子供は身分がないので、裸で描かざるをえなかったのだという。 絵巻物で幼児が裸で描かれたのは、現世の身分が通用しない地獄で亡者が裸で描かれたと同様に、 幼児が現世では「尊卑」の区別のない、身分標識をもたない存在であったことから、絵師は幼児を裸で描かねばならなかったと考えられるのである。P47
子供が裸で描かれた理由としては、ちょっと首をかしげたくもなる。
というのは老人も責任無能力者としながら、 老人は着衣で描かれているからだ。 地獄に行くと身分を剥奪されるので、地獄絵ではみな裸で描かれるということで理由付けされている。 ここはあまり深く追求しないことにしよう。 これまでの検討によって、7歳以下の幼児が近世社会のなかでどのようにみられていたかがある程度明らかになったと考える。 すなわち、7歳以下は服忌令の対象外という考えと、7歳以下は絶対責任無能力者という考えが、近世社会に広く浸透し、7歳以下が特権化して、 7歳が境界年齢として一般的に認識されるようになったといってよいのである。 P85
という指摘は納得する。とすると、子供観がいつ変化し、なぜ変化したのかが問われる。
子供が顧みられなかった事例として、 本書は捨て子を取り上げる。つまり、生後すぐに子供は簡単に捨てられて、犬に食われたり牛馬に踏みつけられたりする例が多かった。 これは中世までは人力への評価が低く、自然の力への畏怖がはびこっていたことも関係するのだろう。また、幼児殺しも頻繁だったという。 とにかく幼い命はきわめて軽かったのである。 親には子供への生殺与奪の権利あると考えられており、捨て子は親が育児を放棄したのだから、
社会はあえて捨て子を保護する必要はないと考えられていた。
それに対して、迷子は親が放棄したのではないから、保護して親を探す必要があった。 現代からすると、実に残酷な話だが、当時は人間の命も牛馬の命も同じであり、人間だけが特別だとは見なされてなかったのだろう。 だいたい人間愛など近代の産物なのだから、当然と言えば当然の対応かもしれない。 子供への視線とは、家に基盤を持つものだ。筆者が次のように言うのは妥当だろう。 捨子の蔓延や捨子対策の不備は、庶民の家が未成熟で継続性をもたず、不安定であったことにその根因を求めることができる。 そうした社会では当然幼児への関心は低く、ましてや幼児死亡率がきわめて高かったから、 幼児は社会的にはとりかえのきく存在としかみられなかったのである。 P111
中世から近世にかけて、生産力が向上し、生産組織たる家が継続性をもつようになって初めて子供の存在が意味を持ってくるのだ。
江戸中期になっても捨て子はいたが、行政組織は捨て子を保護するようになっていた。 生類憐れみの令は、命を大切に扱えるようになったから、 発令が可能になったのであり、ここで言う生類とは人間の命も含まれていたのだ。 そして、筆者は次のように纏めている。 元禄・享保期以降も、なお下層民を中心にして、さまざまな理由で捨子せざるを得ない人々が存在していたことは事実である。 しかし、この時期以降は、都市を中心にして、やがて農村地域でも、庶民の継続性のある家が確立し、幼児を「子宝」とみることが一般化していった。 その結果、子どものいない中間層を中心にして、町や村といった地域社会が、捨子養育の受け皿となりうる条件を成立させていったことに注目したい。 P166
生産力の向上は、人間の自然観も変えさせる。子供への視線の変化を見るだけでも、近代への萌芽が見てとれる。筆者は次のように言う。
近世では、中世のような仏神や天道に依拠する「天道次第」の社会ではなく、人が自分自身で考え、工夫し、行動する、 「人次第」の社会へと大きく転換した。こうした世界観の変容が、幼児に対する考えかたを無関心から保護へと大きく転換させていく原動力になったのである。 その結果、幕府や藩といった政治の場と、家や村・町といった地域社会の両面で、幼児保護に向かっての施策が行われていくことになった。 P189 自然任せ、神任せではなく、作為の誕生であり、人間が自然に働きかけていくようになっている。 あたかも「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」を彷彿させる記述ではないか。(2019.1.30)
参考: 伊藤友宣「家庭という歪んだ宇宙」ちくま文庫、1998 永山翔子「家庭という名の収容所」PHP研究所、2000 J・S・ミル「女性の解放」岩波文庫、1957 末包房子「専業主婦が消える」同友館、1994 梅棹忠夫「女と文明」中央公論社、1988 J・S・ミル「女性の解放」岩波文庫、1957 ベティ・フリーダン「新しい女性の創造」大和書房、1965 楠木ぽとす「産んではいけない!」新潮文庫、2005 シンシア・S・スミス「女は結婚すべきではない」中公文庫、2000 鹿野政直「現代日本女性史」有斐閣、2004 ジャネット・エンジェル「コールガール」筑摩書房、2006 水田珠枝「女性解放思想史」筑摩書房、1979 細井和喜蔵「女工哀史」岩波文庫、1980 モリー・マーティン「素敵なヘルメット」現代書館、1992 R・J・スミス、E・R・ウイスウェル「須恵村の女たち」お茶の水書房、1987 ヘンリク・イプセン「人形の家」角川文庫、1952 斉藤美奈子「モダンガール論」文春文庫、2003 光畑由佳「働くママが日本を救う!」マイコミ新書、2009 奥地圭子「学校は必要か:子供の育つ場を求めて」日本放送協会、1992 フィリップ・アリエス「子供の誕生」みすず書房、1980 伊藤雅子「子どもからの自立 おとなの女が学ぶということ」未来社、1975 ジェシ・グリーン「男だけの育児」飛鳥新社、2001 匠雅音「核家族から単家族へ」丸善、1997 ミシェル・ペロー編「女性史は可能か」藤原書店、1992 マリリン・ヤーロム「<妻>の歴史」慶應義塾大学出版部、2006 シモーヌ・ド・ボーボワール「第二の性」新潮文庫、1997 亀井俊介「性革命のアメリカ」講談社、1989 イーサン・ウォッターズ「クレージ・ライク・アメリカ」紀伊國屋書店、2013 岩村暢子「変わる家族、変わる食卓」中央公論新書、2009 山本理顕、仲俊治「脱住宅−「小さな経済圏」を設計する」平凡社、2018 エイミー・チュア「Tiger-Mother:タイガー・マザー」朝日出版社、2011 清泉 亮「田舎暮らしの教科書」東洋経済新報社、2018 柴田純「日本幼児史」吉川弘文館、2013
|
||||||||||