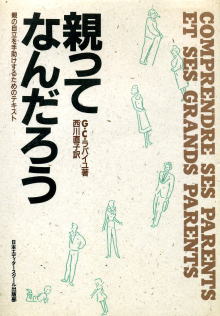著者の略歴−1941年パリ生まれ。パリ大学ソルボンヌで心理学をおさめ、博士号取得。外交官、ミシガン州立大学の客員教授を経て、ソルボンヌ教員。同時に、心理療法にたずさわる。1976年心理学者のトレーニングのため、テラシー研究所設立。1977年「ラバイユ・インターナショナル」を組織し、諸文化の原型をさぐるユンギアンとして調査・研究にあたる。 子供の育て方といった本は、それこそ山のように出版される。 「親子って何だろう」となだいなだが書いているように、親子関係を問うものも少なくはない。 しかし、親自身を問う本は少ない。 子供に対して、親の言うことに従えと言う本はあっても、親の教育方法を教える本は絶無である。 本書は、親をめぐって出色の1冊である。
子供は親に従い、感謝するように教えられる。 産み育ててもらった恩は山より高く、海より深いと教えてきた。 それは、子供が労働力であり、親の老後を見る存在だったからである。 そうした子育ての循環が、農業生産を支えてきたからだ。 農業は繰り返しの産業であり、高齢者の経験がきわめて有効である。 だから、親つまり高齢者が大事だったのだ。 高齢者を大切にしないと、農業の生産力が落ちる。 すると親たちも、結果として子供も、生活に困る。 親=高齢者を大切にする教えは、農業が主な産業だった時代には、誰もが守らなければならない掟だった。 親孝行は文化になっていた。 しかし、近代に入ると、事情が変わった。 高齢者の知恵や経験が、必ずしも有効ではなくなってきた。 むしろ、若者の頭脳のほうが、工業生産の時代を切り開くには役に立った。 工業社会では、親が偉くて、子供は親に従うべきだという、掟が通用力を失い始めた。 高齢者に従わなくても、工業生産は向上した。 むしろ高齢者の言うことをきいていると、社会は発展しない。 高齢者は自分の経験に頼りたがるから、保守的になる。 それでは社会が進歩しない。 高齢者が偉いことを否定する必要がでてきた。 そこで、近代は<人間はみな平等>とは言った。 しかし、工業社会はまだ若くて、新たな親子観を築けなかった。 人間は平等になっても、親子は平等ではなかったのだ。 工業社会になっても、親が偉くて、子供は親に従うべきだ、という掟が残ったままだった。 生活が優先した農業家族と違って、現代の核家族は男女が愛情でつながっている。 結婚したときこそ、愛情だけでも暮らせるが、やがて生活がのしかかってくる。
何かが欠けている、何かがない、何かがうまくいかない。こどもがすべてを具合よくしてくれるだろう、こどもが同時にあなたとなり、私となってくれるだろう、こどもが私たちになれば、私たちは結びつけられ、結束し、連帯できるだろう。こどもが私たちの問題を解決してくれて、けんかをしたり、互いにみつめ合ったり、疲れきったりしないようにしてくれるだろう。こどもが私たちにまた生気を与えてくれるだろう。いま必要なのは、まさにこういったことなのだ……。 ふたりの人間(男と女)が自分の求めるものを相手のなかにみつけられたのだとすれば、なぜ、ふたりで他のところ(こども)をみつめる必要があるでしょうか。親は、自分のパートナーに抱いた誤った期待を、今度はわが子を相手にくり返すことになるのです。自分のパートナー(夫あるいは妻)に期待して得られなかったものを、すべて今度は自分のこどもに期待しようとします。P8 結婚した男女がたがいに愛情にあふれ、相手の存在で満足していれば、子供がいなくても何の不満もない。 愛するからセックスもするだろうが、セックスは愛情の確認である。 数え切れないほどセックスをするだろうが、セックスと子供は関係ない。 子供の誕生につながるのは、ほんの数回、まさに例外的な場合である。 いまではセックスしても子供はできない。 多くの男女は、避妊をしてセックスをしている。 セックスが男女の関係性の確認だからだ。 にもかかわらず、結婚した男女は子供をもとうとする。 とすれば、子供をもつ理由は、筆者が言うように、自分や相手の存在に不満を持ったからだろう。 親になるのは、人間として不足感があるからだ。 それを子供という他人で埋めようとしているのだ。 しかし、パートナーで埋められないものを、子供で埋められるだろうか。 子供は生まれることを望んで、生まれてきたわけではない。 親たちが自分の意志で、子供をもったのだ。 にもかかわらず、育ててもらったことを感謝せよとは、どういうことだろうか。 ふつう自分の意志でなしたことは、自分が責任を取るのであって、相手に何か要求することはない。 子供に対してだけは、親に従えと親は言うのである。 人間はみな平等だ、と近代は言った。 当初、ここでいう人間に、女性は入っていなかった。 いまでは女性も人間である。 しかし、子供はいまだに人間の内に入れてもらえない。 親たちに躾られ、恩着せがましく育てられている。 実際は、子供の存在が親を癒し、親を教育しているのだ。 私たちを産んだ生物学的親であるという事実は、なにも、親に所有権を与えるものではありません。親にわからせてあげなくてはならないことは、親が私たちを人間として、パートナーとしてあつかえばあつかうほど、親と私たちのあいだのトラブルは少なくなる、ということです。反対に、親がこどもを失うのを恐れれば恐れるほど、家庭は牢獄に変わり、こどもは逃げ出したくなるのです。 現在、文化はおそらく変化しつつあります。かつては、血と肉のつながり、生物学的な所有権、遺伝といったものがすべてであり、それが至上の価値とされていました。いまでは、個人の尊重、こどもをもちたいという意図、やがてこどもの自立を受けいれるための配慮、こういったものが、こどもがはたして自分のこどもなのかどうかを知ることよりも、もっと重要なことなのです。望んで親になった親、精神的・情緒的な親であることが、生物学的あるいは社会的親であることよりも、いっそう重要になっています。P102 筆者は子供に対して、親との付き合いかたを書き連ねている。 すべてもっともである。 親が人間として自分の人生を生きることと、親としての役割に生きることは違う。 親役割とは、親が好むと好まざるにかかわらず、社会的に認められた親の義務なのだ。 親は自分の人生を生きるべきだ。 親が親役割果たすことに懸命になっている場合は、子供は親から距離を取ればいい。 親を醒めた目で見れば、親の愚かさが判る。 親が親役割を果たすのではなく、親が自分の人生を生きようとしているときだけ、親子はパートナーとなり得るという。 親の背中を見て育つという。 親は自分の生き方をしていれば、子供はだまっていても、自分の生き方を捜してくる。 親が子供を教育しようとすると、子供との関係は破綻するのだ。 本書は当たり前のことを言っているに過ぎないが、こうした視点を提示している本は少ない。 ずいぶん昔に出版されているが、いまこそ読む価値がある。 (2009.12.30)
参考: M・ヴェーバー「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」岩波文庫、1989 G・エスピン=アンデルセン「福祉国家の可能性」桜井書店、2001 G・エスピン=アンデルセン「ポスト工業経済の社会的基礎」桜井書店、2000 芹沢俊介「母という暴力」春秋社、2001 イヴォンヌ・クニビレール、カトリーヌ・フーケ「母親の社会史」筑摩書房、1994 末包房子「専業主婦が消える」同友館、1994 下田治美「ぼくんち熱血母主家庭 痛快子育て記」講談社文庫、1993 須藤健一「母系社会の構造:サンゴ礁の島々の民族誌」紀伊国屋書店、1989 エリザベート・パダンテール「母性という神話」筑摩書房、1991 斉藤環「母は娘の人生を支配する」日本放送出版協会、2008 ナンシー・チョドロウ「母親業の再生産」新曜社、1981 石原里紗「ふざけるな専業主婦」新潮文庫、2001 石川結貴「モンスター マザー」光文社、2007 イヴォンヌ・クニビレール、カトリーヌ・フーケ「母親の社会史」筑摩書房、1994 梅棹忠夫「女と文明」中央公論社、1988 J・S・ミル「女性の解放」岩波文庫、1957 ベティ・フリーダン「新しい女性の創造」大和書房、1965 ジェーン・バートレット「「産まない」時代の女たち」とびら社、2004 楠木ぽとす「産んではいけない!」新潮文庫、2005 R・J・スミス、E・R・ウイスウェル「須恵村の女たち」お茶の水書房、1987 荻野美穂「中絶論争とアメリカ社会」岩波書店、2001 ヘンリク・イプセン「人形の家」角川文庫、1952 スーザン・ファルーディー「バックラッシュ」新潮社、1994 井上章一「美人論」朝日文芸文庫、1995 ウルフ・ナオミ「美の陰謀」TBSブリタニカ、1994 杉本鉞子「武士の娘」ちくま文庫、1994 ジョンソン桜井もよ「ミリタリー・ワイフの生活」中公新書ラクレ、2009 佐藤昭子「私の田中角栄日記」新潮社、1994 斉藤美奈子「モダンガール論」文春文庫、2003 光畑由佳「働くママが日本を救う!」マイコミ新書、2009 エリオット・レイトン「親を殺した子供たち」草思社、1997 奥地圭子「学校は必要か:子供の育つ場を求めて」日本放送協会、1992 フィリップ・アリエス「子供の誕生」みすず書房、1980 伊藤雅子「子どもからの自立 おとなの女が学ぶということ」未来社、1975 ジェシ・グリーン「男だけの育児」飛鳥新社、2001 高倉正樹「赤ちゃんの値段」講談社、2006 デスモンド・モリス「赤ん坊はなぜかわいい?」河出書房新社、1995 ジュディス・リッチ・ハリス「子育ての大誤解」早川書房、2000 フィリップ・アリエス「子供の誕生」みすず書房、1980 伊藤雅子「子どもからの自立 おとなの女が学ぶということ」未来社、1975 エリオット・レイトン「親を殺した子供たち」草思社、1997 ウルズラ・ヌーバー「<傷つきやすい子ども>という神話」岩波書店、1997 塩倉裕「引きこもる若者たち」朝日文庫、2002 ピーター・リーライト「子どもを喰う世界」晶文社、1995 ニール・ポストマン「子どもはもういない」新樹社、2001、 杉山幸丸「子殺しの行動学:霊長類社会の維持機構をさぐる」北斗出版、1980 矢野智司「子どもという思想」玉川大学出版部、1995 瀬川清子「若者と娘をめぐる民俗」未来社、1972年 赤川学「子どもが減って何が悪い」ちくま新書、2004 浜田寿美男「子どものリアリティ 学校のバーチャリティ」岩波書店、2005 ロイス・R・メリーナ「子どもを迎える人の本」どうぶつ社、2005 宮迫千鶴「ハイブリッドな子供たち」河出文庫、1987 エーバーハルト・メービィウス「子ども共和国」風媒社、1987 J・F・グブリアム、J・A・ホルスタイン「家族とは何か」新曜社、1997 下田治美「ぼくんち熱血母主家庭」講談社文庫、1993 吉廣紀代子「非婚時代」朝日文庫、1987 匠雅音「核家族から単家族へ」丸善、1997
|
|||||||||||||||