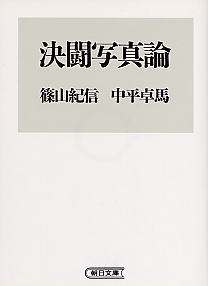著者の略歴−篠山紀信:写真家。1940年東京生まれ。1963年日大芸術学部写真学料卒。1961年日大在学中ライトパブリンティ写真部入社。1968年退社後フリー。主な受賞歴、日本写真批評家協会新人賞、講談社出版文化賞、芸術選奨文部大臣新人賞、毎日芸術賞など。主な写真集に「NUDE 篠山紀信」「オレレ・オララ」「スター106人」「激写・135人の女ともだち」「シルクロード」全8巻、「建築行脚」「シノラマ・ニューヨーク」「Water Frui」「Santa Fe」「Tokyo Nude」「Tokyo未来世紀」「少女革命」「篠山紀信二ユース」全4巻、「アンナ愛の日記」など多数。 中平卓馬(なかひら たくま):写真家、写真評論家。1938年東京生まれ。1963年、東京外語大スペイン語料卒。「現代の眼」編集部入社。1965年同編集部退社とともにフリー・カメラマンとなる。1968年、同人誌「PROVOKE」を多木浩二らと創刊。日本写真批評家協会新人賞受賞。主な写真集、評論集に 「来るべき言葉のために」「なぜ植物図鑑か」「新たなる凝視」 ほか。 1976年の1年間、「アサヒカメラ」に連載したものを、1977年9月に単行本として刊行された。 本書は、それを1995年に文庫化したものである。 決闘とは、篠山紀信が写真を掲載し、中平卓馬が文章を書いて、両者を並べたことを意味するのだろう。
その後の大活躍は周知である。 中平卓馬も写真家と言うことになっている。 が、「現代の眼」の編集部にいたこと、また本書で文章を書いていることからも判るように、写真評論家といったほうがいい。 優れた映像作家は、映像で勝負するものである。 篠山紀信氏の写真についてであるが、小さな文庫版であること、印刷や紙質が悪いことなどによって、残念なことに写真の語るイメージは伝わってこない。 それにたいして、文章のほうは小さな活字でびっしりと組まれているので、文字の訴えるほうがはるかに強い。 そうした意味では、不公平な決闘である。 中平卓馬氏は文章を書くだけで、自分の写真を掲載してはいない。 が、彼の写真に対する好みははっきりと言っている。 彼は19世紀の末に、パリを撮し続けた写真職人ユジェーヌ・アッジェの写真が好きだという。 その理由は、ただパリの風景をそのまま撮したからだそうだ。 当時の写真は感度が低く、1分程度以上の長時間露光をしなければ、写真にならなかった。 そのため、今日のように何でも撮すことができず、動かないものしか写せなかった。 結果として、アッジェの写真には人物が登場せず、パリの街並みだけが定着されることになった。 また、同じようなスタンスで写真をとった人物に、アメリカのウォーカー・エヴァンスがいる。 中平卓馬氏はこの2人を好みとしているが、何とつまらない好みであることか。 これでは単なる記録写真ではないか。 中平卓馬氏によれば、個性とか主体性といったことは、歴史や社会がつくるものであって、当人のものとしては存在しないと言う。 いま、私が問題にしているのはけっして政治的次元にのみかかわるものではない。世界の中での、歴史の中での人間の在り様についてである。<私><主体>は、それがかってにそう思い込んでいるようには世界の、歴史の一方的な創造主としての<主体>などではなく、それ自体また世界の、歴史の<客体>でもあるのだということ、そのような認識がいわゆる<私>論者には欠落している。彼らは<私>というイリュージョンにしがみついて生きているだけである。P78
私は<個性>あるいは<主体>なるものが観念の中、妄想の中でしか存在しないと言うためだけにいささか回り道をしてしまったようだ。私には<個性><主体>による表現に固執する芸術主義者たちの呟きが水槽の中の金魚が吐き出す気泡のように他愛もなく幸福で、しかも滑稽に見える。オレはオレであるなどと信じながらも、世界はそのような幸福な者たちとは無縁にドラスティツクに進展する。P215 中平卓馬氏はロラン・バルトを引用しながら、自己の説を補強していく。 が、この行く先は表現者の否定になりかねない。 そこでは写真をとる行為さえ、不可能になってしまう。 そこで、中平卓馬氏は彼とはまったく資質の違う写真家である篠山紀信をひっぱりだす。 篠山紀信はカメラ小僧といわれるごとく、とにかく写真をとりまくるので有名である。 本書の最後にのっている対談では、2週間の旅行で150本の写真をとったという。 大ざっぱに見ても、1日10本の写真をとっている計算である。 私の旅行では1日平均4〜5本だが、それでも常にシャッターを押さないと4〜5本は撮れない。 10本というと、食事やトイレに行っている時間以外は、常にファインダーを覗いていることになる。 いかに大量に撮っているかが判る。 しかし、大量に写真を撮ることは、シャッターを押し続ければいい。 だから、体力さえあれば可能である。 問題は、写真を選ぶときである。 150本のフィルムから5400カットの写真ができるが、そのすべてを見せることはできない。 写真家がその中から何枚かを選ぶ。 その選ぶ行為のなかに主体が入ってしまうのである。 それは彼も知っている。 そこで彼は写真家の役割を次のように言う。 主体はやはりある。世界とのせめぎ合い、その対抗性として主体はある。主体は不断に樹立されねばならない。その主体が語る。写真においては、すでにくどいように言った工作者、演出家としての写真家がその主体である。写真家は一枚の写真を放り出し、みずからは語らない。すべてを読者の勝手な想像にまかせる。読者、写真を見る者が勝手にその写真に写しとどめられた事物、世界の断片との対話を続ければそれでよいのだ。P231 工作者にはオルガナイザー、演出家にはアジテーターとルビを振っている。 彼の言い分はビジュアルな表現にはすべて当てはまってしまう。 絵画だって画家はモチーフを説明できず、見る人に感じてもらう以外に方法はない。 文字で言うのでない限り、いや文字で語っても、コミュニケーションとは受け手の想像力に負っている。 だから、中平卓馬氏の言い分では写真のことを言っていることにはならない。 中平卓馬氏の言に従えば、記録写真やいわゆる職人の仕事を、最上に評価することになってしまう。 表面的には、なにかとても説得的ではある。 が、近代の意味を深いところで語らずに、流行にのった通俗的な話に聞こえてくる。 やはり優れた表現には、人間に感動を与える何かがある。 それはまぎれもなく一人の人間の仕事である。
参考: ロバート・スクラー「アメリカ映画の文化史 上、下」講談社学術文庫、1995 ポーリン・ケイル「映画辛口案内 私の批評に手加減はない」晶文社、1990 長坂寿久「映画で読むアメリカ」朝日文庫、1995 池波正太郎「味と映画の歳時記」新潮文庫、1986 佐藤忠男 「小津安二郎の芸術(完本)」朝日文庫、2000 伊藤淑子「家族の幻影」大正大学出版会、2004 篠山紀信+中平卓馬「決闘写真論」朝日文庫、1995 ウィリアム・P・ロバートソン「コーエン兄弟の世界」ソニー・マガジンズ、1998 ビートたけし「仁義なき映画論」文春文庫、1991 伴田良輔ほか多数「地獄のハリウッド」洋泉社、1995 瀬川昌久「ジャズで踊って」サイマル出版会、1983 宮台真司「絶望 断念 福音 映画」(株)メディアファクトリー、2004 荒木経惟「天才アラーキー写真の方法」集英社新書、2001 奥山篤信「超・映画評」扶桑社、2008 田嶋陽子「フィルムの中の女」新水社、1991 柳沢保正「へそまがり写真術」ちくま新書、2001 パトリシア・ボズワース「炎のごとく」文芸春秋、1990 仙頭武則「ムービーウォーズ」日経ビジネス人文庫、2000 小沢昭一「私のための芸能野史」ちくま文庫、2004 小沢昭一「私は河原乞食・考」岩波書店、1969 赤木昭夫「ハリウッドはなぜ強いか」ちくま新書、2003 金井美恵子、金井久美子「楽しみと日々」平凡社、2007 町山智浩「<映画の見方>がわかる本」洋泉社、2002 藤原帰一「映画のなかのアメリカ」朝日新聞社、2006 バーナード・ルドルフスキー「さあ横になって食べよう:忘れられた生活様式」鹿島出版会、1985 瀬川清子「食生活の歴史」講談社学術文庫、2001 西川恵「エリゼ宮の食卓 その饗宴と美食外交」新潮文庫、2001 菊池勇夫「飢饉 飢えと食の日本史」集英社新書、2000 アンソニー・ボーデン「キッチン・コンフィデンシャル」新潮社、2001
|
|||||||||||||||